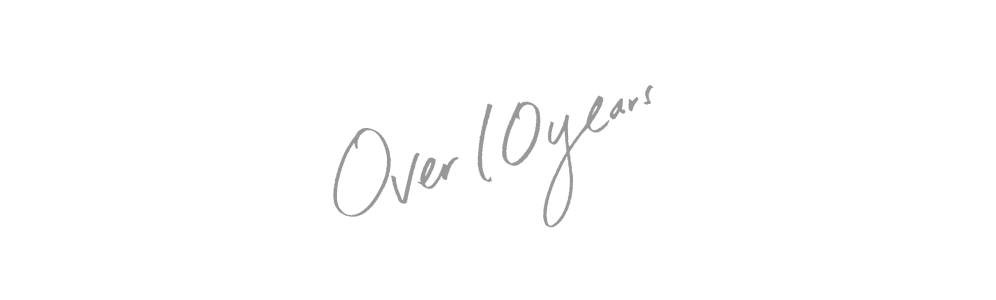
Over 10 Yearsは、誕生から10年を経たKINTOのロングセラーアイテムにフォーカスして、ものづくりに込められたストーリーを届ける企画です。今回は2006年に発売したUNITEAのデザインを手がけるプロダクトデザイナー柴田文江さん、KINTO企画開発チーム西奈美と当時を振り返りながら、ものづくりの背景に迫ります。
UNITEAが生まれた背景
—商品を開発した経緯を教えてください。
西奈美:当時のKINTOはヨーロッパの商品を輸入する事業もあり、日本のマーケットを色々な角度から見ていました。お茶を淹れる道具といえば陶磁器の急須が主流で、ガラスのティーウェアは海外製の装飾的で、エレガントなデザインのものがほとんどでした。ファッションやライフスタイルが、よりシンプルでカジュアルになっていく時代に合うティーポットを作りたい、という思いが開発の出発点となりました。
西奈美:当時のKINTOはヨーロッパの商品を輸入する事業もあり、日本のマーケットを色々な角度から見ていました。お茶を淹れる道具といえば陶磁器の急須が主流で、ガラスのティーウェアは海外製の装飾的で、エレガントなデザインのものがほとんどでした。ファッションやライフスタイルが、よりシンプルでカジュアルになっていく時代に合うティーポットを作りたい、という思いが開発の出発点となりました。


柴田:2004年頃になりますが、デザイン学校で非常勤講師をしている時に、教え子がKINTOに入社したことがありました。それがきっかけになったかはわかりませんが、それからしばらくたって、ガラス素材で新しいティーウェアを作りたいとお話をいただきました。その時印象に残っていたのが、ガラスのカップで温かいものを飲むという習慣が日本ではあまりなかったということです。そこから、誰もが日常的に使えるガラスのティーセットが出来たらいいなと考えていきました。
西奈美:デザインを依頼する際に、KINTOから柴田さんにお伝えしたのは、一人一人が好きなお茶を好きな茶器で飲む「個茶」というスタイルです。普段使いできる安心感があって、女性でも男性でも使いやすいということ、そして、リッド、ストレーナー、ジャグなど、それぞれのアイテムの口径を揃えることで、異素材からなるパーツを組み合わせてフレキシブルに使えるということでした。
柴田:そうでしたね。パーツをカスタマイズできるようなシステマティックなもので、ユニセックスに普段使いできてるものをと、デザインを考えていきました。そこでポイントになったのが「グリップ」のデザインでした。当時のガラスのカップは人差し指、中指、親指で持ち、残りの指を立てて飲むような仕様でしたが、UNITEAでは4本の指でホールドしてガシッと持てるようにハンドルを大きくすることで、ガラスのカップが特別なものではなく、暮らしの中に入るようにしたいと思いました。
西奈美:デザインを依頼する際に、KINTOから柴田さんにお伝えしたのは、一人一人が好きなお茶を好きな茶器で飲む「個茶」というスタイルです。普段使いできる安心感があって、女性でも男性でも使いやすいということ、そして、リッド、ストレーナー、ジャグなど、それぞれのアイテムの口径を揃えることで、異素材からなるパーツを組み合わせてフレキシブルに使えるということでした。
柴田:そうでしたね。パーツをカスタマイズできるようなシステマティックなもので、ユニセックスに普段使いできてるものをと、デザインを考えていきました。そこでポイントになったのが「グリップ」のデザインでした。当時のガラスのカップは人差し指、中指、親指で持ち、残りの指を立てて飲むような仕様でしたが、UNITEAでは4本の指でホールドしてガシッと持てるようにハンドルを大きくすることで、ガラスのカップが特別なものではなく、暮らしの中に入るようにしたいと思いました。

—当時どのような思いでデザインされたのでしょうか。
柴田:もちろんデザイナーとしては長く愛されて欲しいと思っているわけですが、それは狙ってできるものではありません。最近は包丁などのデザインもしていますが、それまで家電などの工業製品を中心にデザインしてきて、中にメカが入っていない、形だけで差別化を求められる製品は初めてでした。売れなかったらデザインのせいだと思って、最初はドキドキしていました(笑)。
でも食器のような日用品をデザインしたいという思いはありましたので、ご依頼をいただいた時はとても嬉しかったです。
—デザインをする上で苦労した点はありますか。
柴田:実際に進めてみると口径を合わせて、複数の製品をデザインすることは難しかったです。容量の違うものを作る時に、全体の大きさを自由に変えてもいいのであれば、相似形で作ることでファミリーになりますが、口径を変えずに倍の容量のものを作るのは意外と難しいんですよね。
まずは形に大小をつけても、キャラクターのあるモチーフを探すことから始めました。直線的でシャープなものも考えたのですが、当時はガラス素材のカップでお茶を飲むという習慣があまりなかった時代です。それだと抵抗をもたれてしまうのではと思いました。もう少しフレンドリーで使いやすい感じにしたいと思い、曲率を変えることでそれぞれの容量も調整できて、見た目にも優しい下ぶくれのモチーフを考えました。そうすることでサイズの違う展開や用途が変わっても、ファミリー感を出せるのではと仮説を立てながら検証していきました。
柴田:もちろんデザイナーとしては長く愛されて欲しいと思っているわけですが、それは狙ってできるものではありません。最近は包丁などのデザインもしていますが、それまで家電などの工業製品を中心にデザインしてきて、中にメカが入っていない、形だけで差別化を求められる製品は初めてでした。売れなかったらデザインのせいだと思って、最初はドキドキしていました(笑)。
でも食器のような日用品をデザインしたいという思いはありましたので、ご依頼をいただいた時はとても嬉しかったです。
—デザインをする上で苦労した点はありますか。
柴田:実際に進めてみると口径を合わせて、複数の製品をデザインすることは難しかったです。容量の違うものを作る時に、全体の大きさを自由に変えてもいいのであれば、相似形で作ることでファミリーになりますが、口径を変えずに倍の容量のものを作るのは意外と難しいんですよね。
まずは形に大小をつけても、キャラクターのあるモチーフを探すことから始めました。直線的でシャープなものも考えたのですが、当時はガラス素材のカップでお茶を飲むという習慣があまりなかった時代です。それだと抵抗をもたれてしまうのではと思いました。もう少しフレンドリーで使いやすい感じにしたいと思い、曲率を変えることでそれぞれの容量も調整できて、見た目にも優しい下ぶくれのモチーフを考えました。そうすることでサイズの違う展開や用途が変わっても、ファミリー感を出せるのではと仮説を立てながら検証していきました。
UNITEAのあゆみ
ー発売から現在にいたるまで、改良した点があれば教えてください。
西奈美:2006年に最初の製品を発売しましたが、2008年にはガラス工場を見直しました。ティーポットの製造ラインは、完全な手吹きから半オートメーションに変えて、より品質が安定するようになりました。そして、2009年にはプラスチックのストレーナーも、より熱に強い素材へと変更しましたが、耐熱性と透明度の両方を備えた素材を求めて、2012年にガラスのような見た目でありながら、扱いやすさを持ち合わせたストレーナーに進化しました。
柴田:プラスチックのストレーナーには均一に穴があいていて、これまで私自身色々な工業製品を手がけてきた中でも、日用品の価格でここまで手のこんだことをしている製品は他にはありません。お湯を注いだ時に、ストレーナーの中で対流がおこり、細かな穴から均一に抽出しないと美味しいお茶にはなりません。曲面にこれだけきれいな穴をあけるのは難しいはずなんです。私自身なにげなく提案したのですが、仕上がってきた時には、よく実現できたなと関心しました。
西奈美:生産性と使い心地、デザイン、全てのバランスを維持することは、商品開発をする上で常に心がけていることですが、UNITEAについては柴田さんのデザインをどこまで実現できるか、工場と試行錯誤を繰り返しました。工場は生産効率を考えて、作りやすいようにデザインを変えようとするのですが、私たちはデザイナーさんの思いと意図をきちんと汲み取り、コスト面も考慮しつつ、安定した品質で生産し続けられるよう努めています。
西奈美:2006年に最初の製品を発売しましたが、2008年にはガラス工場を見直しました。ティーポットの製造ラインは、完全な手吹きから半オートメーションに変えて、より品質が安定するようになりました。そして、2009年にはプラスチックのストレーナーも、より熱に強い素材へと変更しましたが、耐熱性と透明度の両方を備えた素材を求めて、2012年にガラスのような見た目でありながら、扱いやすさを持ち合わせたストレーナーに進化しました。
柴田:プラスチックのストレーナーには均一に穴があいていて、これまで私自身色々な工業製品を手がけてきた中でも、日用品の価格でここまで手のこんだことをしている製品は他にはありません。お湯を注いだ時に、ストレーナーの中で対流がおこり、細かな穴から均一に抽出しないと美味しいお茶にはなりません。曲面にこれだけきれいな穴をあけるのは難しいはずなんです。私自身なにげなく提案したのですが、仕上がってきた時には、よく実現できたなと関心しました。
西奈美:生産性と使い心地、デザイン、全てのバランスを維持することは、商品開発をする上で常に心がけていることですが、UNITEAについては柴田さんのデザインをどこまで実現できるか、工場と試行錯誤を繰り返しました。工場は生産効率を考えて、作りやすいようにデザインを変えようとするのですが、私たちはデザイナーさんの思いと意図をきちんと汲み取り、コスト面も考慮しつつ、安定した品質で生産し続けられるよう努めています。



西奈美:UNITEAはユニットを組みかえて使える機能的な面もそうですが、ガラス、ステンレス、プラスチック、天然木など、それぞれの素材の質感を愉しんででいただくことができるバリエーションの豊かさも魅力ですよね。
柴田:UNITEA自体が懐深く、異なるサイズ、素材や色を受け入れることができます。自分でデザインしていてもそれはすごく不思議ですね。でも、最初に作った時はそこまで考えていなくて、育てながらこれも似合う、あれも似合うとつくってきて、そんなニュートラルなところもUNITEAらしいところだと思っています。
柴田:UNITEA自体が懐深く、異なるサイズ、素材や色を受け入れることができます。自分でデザインしていてもそれはすごく不思議ですね。でも、最初に作った時はそこまで考えていなくて、育てながらこれも似合う、あれも似合うとつくってきて、そんなニュートラルなところもUNITEAらしいところだと思っています。
(インタビュアー/テキスト 加藤孝司)




